口臭対策で選んでいるガム
私は普段ほとんどガムを噛まないのですが、口臭が気になる場面で稀に使うことがあります。選んでいるのはTrueGum(トゥルーガム)のミントかホワイトです。
TrueGumはデンマークの企業が作っているガムで、甘味料はキシリトールとステビアのみ。
ガムベースの素材にもこだわりありという点が気に入っています。
特にミントとホワイトは甘さが控えめで、「4毒抜き(小麦・甘いもの・植物油・乳製品を避ける生活)」をしている私でも、エチケットのための限定的な場面なら許容できると感じています。
一方で、他のフレーバーは甘みがしっかりしているので、甘いものを避けたい人にはミントかホワイトを選ぶ方がおすすめです。
TrueGumを切らしてしまったとき
とはいえ、TrueGumを常備できていないこともあります。そんな時には、市販のガムをやむを得ず噛むこともあります。ただし多くの市販品には人工甘味料が入っています。
私は人工甘味料を摂りたくないため、甘味が残っている間は唾液を飲み込まず、味が弱まってくるまで口から出すようにしています。それでも、その後に残るわずかな甘味成分を含む唾液を飲み込むだけで、お腹の膨満感や不快感を強く感じることがあります。
4毒抜き前との違い
以前は眠気覚ましや気分転換のために、気軽に市販のシュガーレスガムを噛んでいました。当時は「便利で体にやさしい」と思い込んでいましたが、今振り返るとお腹の張りや軽い胃もたれを感じることも多かったのです。4毒抜きを始めてからは体調がクリアになり、その変化をより敏感に捉えられるようになったのだと思います。
興味深いのは、この不快感が「4毒抜き」を始める前にはほとんどなかったという点です。ごく微量でも体が違和感を示すようになったのは、人工甘味料の影響を受けやすくなったというより、体が以前より反応しやすくなったのだと思います。
人工甘味料と健康への影響(研究エビデンスより)
人工甘味料は「低カロリーで安全」と言われることも多いですが、近年の研究を見ると注意が必要だと感じます。
腸内環境の乱れは便秘や下痢といった日常的な不調につながる可能性がありますし、血糖コントロールの乱れは肥満や糖尿病リスクの上昇とも関連します。また、気分の落ち込みや不安感は、仕事や人間関係に影響することも少なくありません。こうした点を考えると、人工甘味料の影響は単なる「カロリーゼロ」の問題にとどまらないと感じます。
腸内細菌への影響
2014年にNature誌で発表された研究では、人工甘味料が腸内細菌を乱し、血糖コントロールに悪影響を与える可能性が報告されました。
2023年のFrontiers in Nutritionのレビュー論文では、スクラロースやアセスルファムKが腸内フローラの多様性を低下させる可能性があるとまとめられています。
代謝・心血管リスクへの影響
2022年にBMJ誌で発表されたフランスの大規模調査では、人工甘味料を多く摂取する人ほど心血管疾患リスクが高い傾向が示されました。
**アメリカ心臓協会(AHA)とアメリカ糖尿病協会(ADA)の合同声明(2018年)**でも、人工甘味料の長期的な有効性は明確でなく、むしろ耐糖能やインスリン反応への悪影響が懸念されています。
精神面への影響
2017年にNutritional Neuroscience誌でまとめられたレビューでは、アスパルテームが脳内の神経伝達物質に影響を与え、不安や気分の落ち込みと関連する可能性が指摘されています。
ちなみに、私はガム以外の口臭対策として、ミントティーや緑茶を飲むこと、水分補給をこまめにすることも取り入れています。天然のハーブや食後のうがいもシンプルですが効果的です。こうした習慣を組み合わせると、人工甘味料に頼らずにエチケット対策ができると感じています。
改めて感じた人工甘味料のこわさ
私自身、4毒抜きを始めてから人工甘味料の微量な摂取でも体の変化を強く感じるようになりました。科学的な研究報告と、自分の体感が重なったことで、やはり人工甘味料はできる限り避けたいと考えるようになりました。
もちろん、完全にゼロにするのは難しい場面もありますが、日常的な選択肢としては
・摂取を最小限にする
・可能ならゼロに近づける
という方針が、心身ともに健やかに過ごすためには良いのではないかと思います。
✅まとめ
・人工甘味料入りガムは便利だが、体への違和感を感じやすい
・腸内環境や代謝、精神面に影響を及ぼす可能性が複数の研究で示されている
・体感としても不快感を覚えるようになり、改めて「避けたい」と実感した
私にとっては「非常時のエチケット目的」以外では選ばないようにしています。
もしガムや飲料を口にしたあとに「お腹が張る」「頭が重い」「なんとなく気分が落ち込む」といった違和感があるなら、それは人工甘味料が影響しているのかもしれません。少し意識して選ぶだけでも、体調の変化を実感できる可能性があります。
参考文献(出典リスト)
Suez J, et al. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature. 2014.
Ruiz-Ojeda FJ, et al. Effects of non-nutritive sweeteners on the gut microbiota. Frontiers in Nutrition. 2023.
Debras C, et al. Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the NutriNet-Santé cohort. BMJ. 2022.
American Heart Association and American Diabetes Association. Nonnutritive sweeteners: current use and health perspectives. Circulation. 2018.
Lobach AR, et al. Aspartame and its effects on neurobehavioral health. Nutritional Neuroscience. 2017.
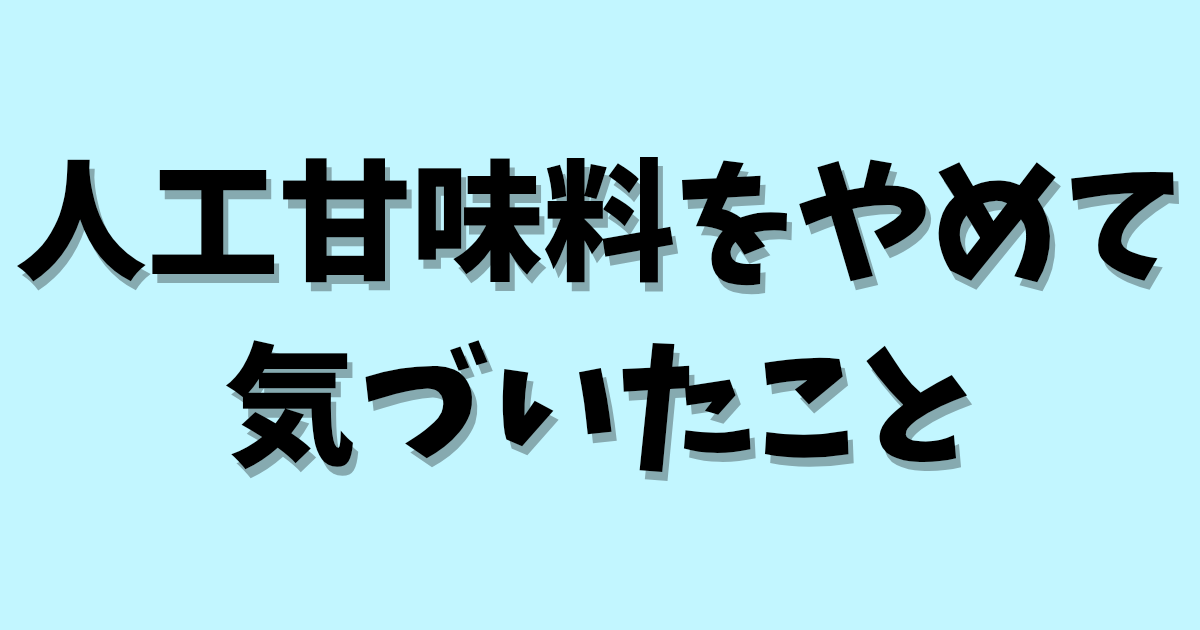
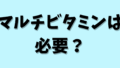
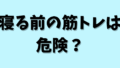
コメント